宮沢賢治をゆっくり読むアート・仏教・ビジネスの交差点へ
岡田基生
ほんとうの「さいわい」とは何だろう
ウェルビーイング、エコロジー、リベラルアーツ──今でこそ注目されるこれらのテーマに、100年前の日本で真剣に取り組み、社会を変えようとした人物がいた。それが宮沢賢治だ。では、もし賢治が現代に生きていたら、どんな未来を描いただろうか?
本書は、賢治を文学者としてだけではなく、「アートの力で社会課題の解決に挑んだ情熱的なソーシャル・イノベーター」として新たに捉え直す試みである。著者が独自に編み出した「熟読の技芸」を通じて、作品の中にある賢治のエッセンスが詰まった一文を丁寧に読み解きながら、これからの社会や私たちの生き方を豊かにするヒントを探っていく。
読者は、『銀河鉄道の夜』に込められた「ほんとうのさいわいとは何か?」という根源的な問いに始まり、『虔十公園林』『農民芸術概論綱要』、そして『ポラーノの広場』へと分け入っていく知的冒険を体験することになる。物語の世界を旅しながら、本当に豊かな社会とはどんなものか、それを自分たちの手でどう実現できるのかを考えていきたい。
著者自身が、哲学・芸術・ビジネスなど、さまざまな領域を横断して思考してきたからこそ描き出せる新しい宮沢賢治像を提示する本書は、賢治研究の書であると同時に、より良い未来を創りたいと願う読者一人ひとりへと、実践的な知恵と勇気を贈る一冊である。「永久の未完成これ完成である」と語った賢治のしなやかな強さは、不安な時代を生きる私たちの背中をそっと押してくれるだろう。
【目次】
はじめに──もしも宮沢賢治が現代に生きていたら
どうすればみんなが楽しめる世界をつくれるか/自分自身の生き方が問われる時代/ソーシャル・イノベーターとしての宮沢賢治/「ゆっくり読む」とはどういうことか
第1章 本当に大切なものを探る旅──童話「銀河鉄道の夜」
人生観が揺さぶられる夜
探求の出発点/カムパネルラの苦悩/他の個の幸福への問い/「みんな」と「みちづれ」の緊張関係
本当の幸福を探る手がかり
みんながカムパネルラだ/「ジョバンニの切符」とは何か/「一念三千」という宇宙観/本当の幸福を探るための実験/なぜブルガニロ博士は登場しなくなったのか
コラム 現在のイギリス海岸
第2章 本当の幸福が感じられる場所──童話「虔十公園林」
杉林で深呼吸する
公園林の物語/森林浴の効能
虔十と賢治
新鮮に感受し、歓びを分かち合うこと/虔十の賢さ/「十力」とは何か
公園林が教えること
自然と人為が調和する人工林/遊びと学びが一体となる場/生命の活かし合いと、それを成り立たせる力
コラム 宮沢賢治と鉱物
第3章 永久の未完成という完成──芸術論『農民芸術概論綱要』
宇宙の構造から幸福を考える
どうすればもっと楽しく暮らせるか/世界のすべてはつながっている/すべては自分の中で起こっている/「こゝろのひとつの風物」としての宇宙/互いが互いを映し合う宇宙/私はすべての出来事の当事者である/あらゆる自己中心性の根源/すべての個が宇宙の主役である/未完成でありながら完成している幸福
幸福の原体験
曠野の饗宴/「自分を忘れる」とはどういうことか/「楽しい/たのしい」とはどういうことか
幸福はどのようにして成立するか
賢治の宇宙観と生命観/賢治の幸福観/ポジティブ心理学との関係/「みんな」と「みちづれ」の調和的な関係
コラム 求道の共同体
第4章 大地と人間が織りなす演劇──詩〔生徒諸君に寄せる〕
どうすれば幸福な社会のビジョンを描けるか
賢治の時代認識/詩人の使命/予言と設計の一体性/森羅万象の奏でる音楽/詩は誰に由来するか
賢治の描いたビジョン
「地人芸術」というプロジェクト/「地人の個性」とは何か/大地と人間が織りなすオペラを上演する/地人芸術の実践方法/世界の幸福と地人芸術の関係
アートを生み出す方法
「活動としてのアート」と「生活としてのアート」の関係/創作の前段階――生活としてのアート/無意識の重要性/創作のプロセス――活動としてのアート/地人芸術の実例/風とゆききすること/雲からエネルギーをとること
賢治が生み出した秩序
「コスモス」としての美/「われらの美」によって乗り越えられる四つの課題/「イーハトーヴ」というプロジェクト/「イーハトーヴ」という言葉の成り立ち/地人芸術を継承する/私の実践
コラム 言葉の音、音の言葉
第5章 自分たちの手で広場をつくる──童話「ポラーノの広場」
幻滅から始まる物語
どのようにビジョンを実現すればよいか/なぜ広場が重要なのか/「ポラーノの広場」の物語/三つのポラーノの広場/羅須地人協会の活動
理想主義の罠
削除されたキューストの激励/晩年の賢治の心境/「雨ニモマケズ」の先へ/本当の謙虚さはどこから生まれるか
変革の技芸
工夫──答えのない課題に向き合う/饗宴──他の個と共に生命を養う/共演──他の個と共に役割を果たす/方便──相手に合わせて表現する/これからの豊かさを実現する鍵
コラム 時を超えたティーパーティー
おわりに──イーハトーヴの物語は続く
著者について
岡田基生(おかだ・もとき)独立研究者。宮沢賢治学会会員。修士(哲学)。1992年生まれ、神奈川県出身。ケルン大学哲学部への交換留学を経て、上智大学文学部哲学科を卒業。同大学院哲学研究科で大正・昭和初期の哲学を研究。修了後、人文知を社会変革に活かす道を探るため、民間企業で働きながら、哲学・アート・ビジネス・教育の領域を横断する探究を続ける。IT企業を経て、カルチュア・コンビニエンス・クラブに入社し、代官山 蔦屋書店の人文・ビジネスフロアのマネージャーを経験。現在は出版社で書籍編集に携わる。宮沢賢治についての研究の成果を論考やワークショップなどの形式で発表するほか、岩手県花巻市内の中学校・高校などで10代に向けた講演も実施している。共著に『批評の歩き方』(赤井浩太・松田樹責任編集、人文書院、2024年)がある。
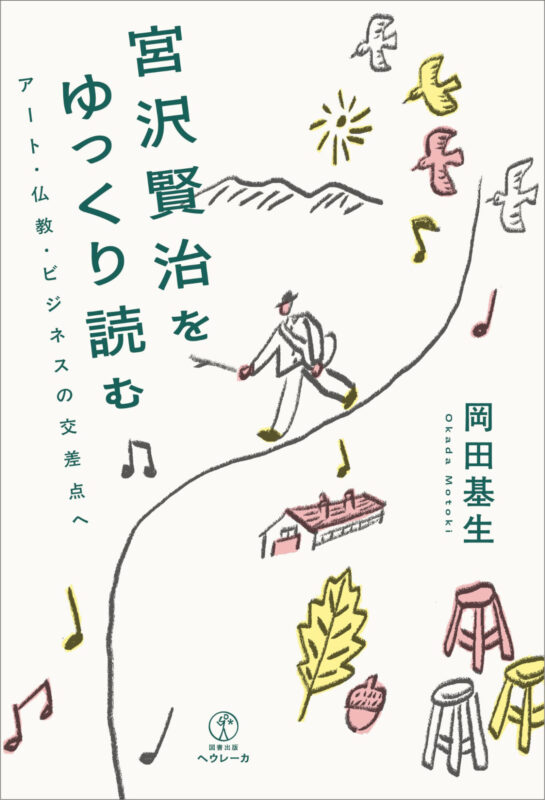
宮沢賢治をゆっくり読む アート・仏教・ビジネスの交差点へ
岡田基生
装丁:末吉亮(図工ファイブ)
2025年12月10日・刊 定価:2,200円+税 272ページ ISBN: 978-4-909753-24-3 並製
